「食べる」とは何か──コンビニ弁当と命の重さ
ある本で、衝撃的な養豚農家の話を読みました。
その内容とは、
賞味期限切れのコンビニ弁当を、捨てるのが惜しいという理由で
ブタの餌にしたところ、数か月後に母豚の死産や奇形が相次ぎ、
羊水はコーヒー色に濁り、250頭もの子豚に影響そうです。
腐っていたわけではない。むしろ「人間が食べても問題なさそう」
な見た目だったという。
この話を読んだとき、私は「食べるとは何か?」と考えました。

添加物と保存料──便利さの代償
コンビニ弁当には、保存料や着色料、pH調整剤など多くの食品添加物が
使われています。
これらは腐敗を防ぎ、見た目や味を保つために必要とされるが、長期的に
摂取することで健康への影響が懸念されています。
もちろん、個々の添加物には使用基準が厳格に定められており、
単体での安全性は確認されています。
しかし、問題は「複合的な摂取」にある気がします。
毎食コンビニ弁当を毎食食べ続けることで、数十種類の添加物が体内に入り、
互いにどのような相互作用を起こすかは、十分に検証されていない。
まるで、異なる薬を同時に飲み続けるようなもの。
安全とされる量でも、積み重なれば思わぬ影響が出る可能性があります。
さらに、栄養バランスの偏りも見逃せません。
加工食品中心の食生活では、ビタミンやミネラルが不足し、「新型栄養失調」に
陥るリスクもあります。
これは、見た目には太っていても、体の中では栄養が足りていないという状態。
命の連鎖に潜む問い
ブタの異常出産は、添加物の影響なのか、栄養の偏りなのか、真因はわかりません。
ただ、命の営みに異変が起きたという事実は、私たちに「食べることの責任」を
問いかけています。
私たちは、何を食べて、どう生きるのか。
便利さの裏にある代償を見つめ直すことは、健康だけでなく、命の尊厳を守ることにも
つながるのではないでしょうか?
「どう選べばいいのか?」──小さな選択が未来を変える
私たちの食卓は、日々の選択の積み重ねでできています。
コンビニ弁当が悪いわけではありません。
忙しい日々の中で、手軽に食事を済ませられることは、現代社会の恩恵でもあります。
ただ、それが「毎食」になったとき、便利さが健康を蝕むリスクに変わってしまします。
では、どうすればいいのか?
小さな選択のヒント
- 週に数回は手作りを 自炊は、食材の質や調味料の量を自分でコントロールできる。たとえ簡単な炒め物でも、素材の味を感じることができます。
- 原材料表示を読む習慣を 表示は多い物順で書かれてます。「何が入っているか」を知ることは、食べる責任の第一歩。見慣れない添加物が多いときは、一度考えましょう。
- “色”や“香り”に惑わされない 鮮やかな色や強い香りは、添加物による演出かもしれない。不自然なものは取り込まないほうが良い。
- “賞味期限”の意味を見直す 長持ちする食品ほど、保存料が多く使われている可能性がある。新鮮なものを、必要な分だけ買う習慣も大切。
食べることは、生きること。
ブタたちの悲劇は、私たちへの静かな警鐘かもしれません。
だからこそ、今日の食卓に、ほんの少しの「意識」を添えてみよう。

参考図書:食卓の向こう側 (2) (西日本新聞ブックレット No. 2)
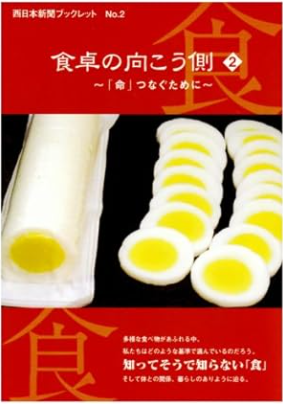


コメント