「重職心得箇条」は、幕末期に佐藤一斎が書いたリーダーシップの心得で、
17条の教えから成ります。
主な内容は、公平さや人材の活用、柔軟な対応、計画性の大切さなどです。
また、小事にこだわらず大局を見据え、部下を信頼し、時勢に応じた判断を
下すことが求められる、といったリーダーの心構えが描かれています。

その中の一つに、祖先から引き継いだ伝統は失ってはならないが、過去からの
「又仕来(きた)り」「仕癖(しくせ)」は「時に従って変えるべき!」
とあります。
仕来り → 習慣、ならわし、慣例
仕癖 → 気性、生まれつき、人に備わっている資質
以前、こんな事がありました。
私の会社では、車通勤が禁止されています。
しかし、ず~と前からみんな、隠れて車通勤をしていました。
たまに新任の上司がくると、注意され一時的に辞めますが、すぐに戻ります。
そんなある日、社員が通勤途中に車の事故で亡くなりました。
「あの時、車通勤をやめておけば・・・」
後悔しても、友人は戻ってきません。
悪しき、「又仕来(きた)り」「仕癖(しくせ)」の典型でした。

また、こんな「仕癖」の笑い話しもあります。
あるお嬢さんが魚の煮つけを作ってくれました。
調理の様子を見ていると、変わったやり方をしています。
そこで聞いてみました。
「何のために、尻尾を切り落とすのですか?」
「私もわかりませんが、母に教わりました」
そこで、横にいるお母さんに聞いたところ、
「私もよくわからないのですが、母がいつもしていたのを見て覚えたのです。
味のしみこみ方が良くなるのではないでしょうか?」と言います。
そこで、おばあさんに聞きました。
「おばあさん、娘さんやお孫さんがあなたに教わった通り、
いつも魚の尻尾を切っていますが、何か理由があるのですか?」と聞きました。
すると、おばあさんは笑いながらこう答えたのでした。
「教えたときに、たまたま私が使っていた鍋が小さかっただけよ」 ・・・笑

私たちは、普段何気なく行っている習慣や慣例の中には、意味を失ったまま
続けているものも少なくありません。
しかし、本来の目的を見直すことで、新たな成長や改善を見いだすことができるのです。
『重職心得箇条』には、そんな視点を養うための教訓が込められています。


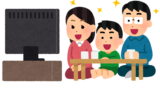

コメント