先日、会社の健康診断を受けました。
結果は、上の血圧が131mmHgで要経過観察!
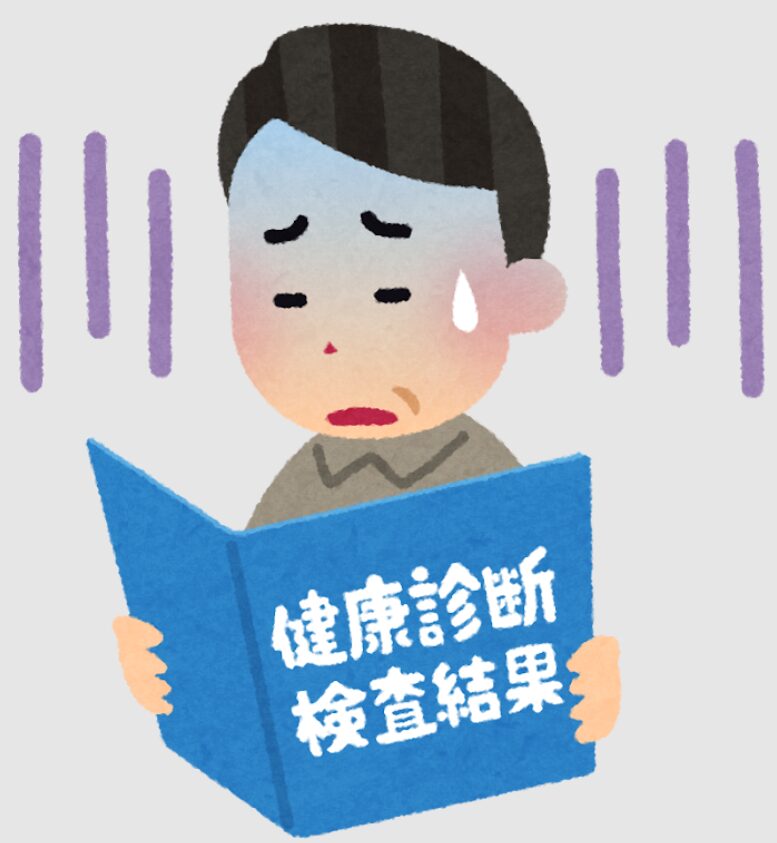
えっ! これまでも同じような血圧でしたが、今回はなぜか経過観察でした。
調べてみると、どうやら血圧基準が少しずつ厳しくなっているようなのです。
私は現在58歳。
年齢とともに血管が硬くなり、自然に血圧が上がるのは当然の生理現象です。
この「上がる傾向」と「下がる基準値」のギャップが私たちに何を意味するのか、
一緒に考えてみましょう。
*基準値の遍歴
かつては「年齢+90」という指標で血圧を測っていた時代もありました。
しかし、現在は140/90mmHgや家庭血圧135/85mmHgなど、
より低い基準が設定されています。
この基準変更は予防医療の進歩を反映していますが、
一部では健康不安を過剰に煽る結果にもなり得ます。
| 時期 | 基準を出した機関 | 基準内容 |
|---|---|---|
| 昔(1960年代以前) | 一般的な目安 | 「年齢+90」を目安に、高血圧を判断。 |
| 1987年 | 旧厚生省 | 収縮期血圧180mmHg、拡張期血圧100mmHg以上を高血圧と定義。 |
| 2000年 | 日本高血圧学会 | 収縮期血圧140mmHg、拡張期血圧90mmHg以上を高血圧と設定。 |
| 2004年 | 日本高血圧学会 | 全年齢で基準を統一し、140/90mmHg以上を高血圧と判断。 |
| 2008年 | 特定検診制度(厚生労働省) | 特定保健指導の基準として収縮期血圧130mmHg以上を設定。 |
| 2014年 | 日本人間ドック学会 | 正常値を収縮期血圧129mmHg以下、拡張期血圧84mmHg以下とし、高血圧は140/90mmHg以上。 |
| 2019年 | 日本高血圧学会 | 基準値を維持(140/90mmHg)し、個別対応の重要性を強調。 |
| 2024年 | 改訂(日本高血圧学会) | 家庭血圧で135/85mmHg以上を高血圧と診断。 |
*年齢と血圧の自然な関係
加齢に伴い、血管の柔軟性が徐々に失われて硬くなり、
それに伴って血圧が上がる傾向があります。
これは健康な老化の一部とも言えます。
しかし、基準値の変化により「必要以上に下げる」ことが
リスクとして浮かび上がってきました。
*降圧剤使用のリスクと考え方
①過剰な血圧低下
血圧を過度に下げることは、脳梗塞や血流障害を引き起こす可能性があります。
②自然な体の変化を考慮
年齢や体質を無視して血圧を一律に管理することは、逆効果となる場合もあります。
*健康管理のための提案
①血圧を下げるよりも、ストレス管理や食事の改善に注力する。
②医師との対話で、自分にとって最適な血圧範囲を見つける。
③基準に振り回されず、自分の体の声を大切にする。
*最後に
変わり続ける基準値に惑わされず、年齢に応じた健康目標を
立てることが大切です。
血圧はあくまで「体の状態を示すひとつのサイン」です。
無理なく自分の体と向き合いましょう!


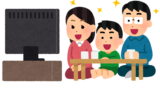

コメント